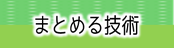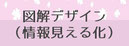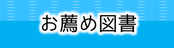図解作家としての私の仕事
企業、個人に関わらず、次の行動を考える上で、課題を洗い出し 情報収集し まとめることは重要です。大切なことは、現状の問題点をじっくり【観察】し、対象のものの課題を想定し絞り込むこと。観察した際のいろいろなデータの中から必要な情報を取り出し、さらに関連した詳細情報を収集しデータベースとして格納。専門的見地からこれら情報を【分析】していくことで、課題をイメージし、これらの情報を論理的に関連づけて【合成】していくことで、解決策がみえてくるでしょう。しかし、解決策は導き出せない場合には、さらに他の関連課題とつなぎ合わせ、異なる角度での解決方法を見つけ出す必要性があります。「説得」よりもむしろ「納得」してもらうことが大切です。多くの人たちが潜在的に持っている「まとめる力」をさらに強化。「考える人材」が活躍することでよりよい社会が形成されることを願っています。まとめる技術で「人を育てる」。それが私の仕事です。
忘れる前に素早く想い出すことを考える
現代情報化社会では、さまざまなメディアを通して多くの知識を得ることができるようになりました。豊富な知識はやがて多くの経験を重ね、新たな知恵を生み出します。新たな知恵は、優れた知能により生かされ数多くの課題の解決を図っていくこといになります。やがてこれらの経験の積み重ねにより「考える知性」が芽生えてくるでしょう。
しかし、人間の記憶能力には限界があります。悲しいかな、新たな知識を取り込むたびに、過去の知識は忘れ去ってしまうのです。とはいえ、多くの情報をコンパクトな形にしてイメージとして取り込めば、情報容量は大いに低減できるのではないでしょうか。覚えたことを忘れるのは人間の得意技。どうせ忘れるのであれば「うまく忘れて」しまった方がいい。忘れることを恐れるのではなく、想い出せないことを恐れたほうがいいのです。
「いかに覚えるか」よりも、「いかに忘れ、いかに想い出すか」。それは「まとめる技術」で解決できるかもしれません。
ことまとめ概念図

ことをまとめる要領
社会にはいろいろ理解できない複雑なことがあっても、時間をかけてきちんと説明されればわかることが多いかと思います。多くの人を前にして、図表を示しながらプレゼンテーションする(紐解き図解)ことで、納得する光景はしばしば見受けられますね。しかし、終わってしばらくすると、徐々に記憶が薄れてしまいます。検索すればこれらの情報を引き出すことは可能ですが、再度読み込まなければなりません。でも事前に、重要なポイントを関連ずけて一目でわかるように(まとめ図解)しておけば、困ることはありません。
とはいえ、ことあるごとにスマホを手にするのも、環境によっては難しいことから、より素早く記憶を引き出したいものです。そこで、覚えやすいシンプルなモデルをイメージしておけば、これを想い出せばいいわけですから、記憶容量が少なくてすむ、ってわけですね。
ことまとめ要点

状況で変わる図解の用途
左右のふたつの図解は、同じ図解でありながら用途が異なるんです。左図は矢印を多用した時系列的な図解であり、これまでの経緯から内容を理解することができるでしょう。一方、右図は全体を捉えた概念的な図解であり、結果を表現しています。内容的には同じであるものの、時間がある人に経緯など詳細を説明する際には左図の「紐解き図解」が、時間がなくが全体の状況を説明する必要があるときには右図の「まとめ図解」が最適です。
このように図解の中にも、その目的と用途によって、まとめる形態が異なるんですね。ただし「まとめ図解」は多くの情報を取り除いていることから、人によっては解釈が異なる場合もあるので注意する必要性があります。これは10年前の図解ですが、2020年の新型コロナ流行により仕事環境や教育環境が激変したことから、未来に向けた新たな仕組みをデザインしなければならないものと考えます。
「日本の論点2011」(文芸春秋社)の巻末特集「日本の実力」の中に「子どもの学力」という記事がありました。教育の専門家ではないので内容の是非には触れませんが、この例を参考に図解の使い分けについて考えてみましょう。
まとめるデザイン
裁判員裁判のあらまし
地域活性化ビジネスモデル提言
各種戦略論を集約したまとめ図
情報システムとビジネスプロセス
業務フローチャート
バランススコアカード+2
VW Beetle 愛好家サイト
円谷幸吉-須賀川市応援サイト
出世前の戦略的HP
思い出せるならば 忘れていいのかもしれません

最初に、私はこの物語のマップを作成してみました。しかし、あまりにも情報が多すぎることから、物語全体をすばやく想い出すことができません。
そこで、複雑な物語、制度、関係を記憶に残す方法を考案してみました。それは、このマップをイメージとしてとらえ、他の形状(メタファ)に置き換えるということ。そして細かい情報を忘れてしまうことです。「ギリシャ神話」は「王」、「仏教」は、「心」という文字に置き換えることができました。
実際には、この文字ですべてが想い出せるわけではありません。しかし、この方法により個人の記憶容量を軽減できることから、脳の記憶の機能を、他の仕事や趣味に使うことができるようにも思います。これは、いうなれば「情報のアナログ的な圧縮と解凍の技術」といえるでしょう。
覚えた知識は、深い無意識層に置き、そして意識の中からは消滅する。やがて、なにかをきっかけに深い記憶の中で小さな揺らぎが起こり、創発的にアイデアがひらめく、というわけです。極論ですが「思い出せるならば、忘れてもいい」とも思うのです。これからの仕事や学習の方法の一つとして、活用されることを期待したいところです。
小林秀雄曰く:メモやテープや知識や理論に頼り、自分の頭で苦労して考えず、「要は......」と簡単にわかろうとするのは「現代の病」。歴史で大切なのは、知識ではなく、出来事が、今のことに感じられるような記憶を呼び覚ます力だ。(2014/3/16読売新聞)
記憶を呼び覚ますためには、どう記憶するかではなく、どう忘れるかという問題に帰着する
そのように思います。(Y. Hasebe)
まとめるデザイン技術の原点
そもそも、考えていることをデザインしようと思い立ったのは、某広島の自動車会社に「もの作りのプレゼンテーション」をしなければならない、という状況に陥ったことに始まる。「釈迦に説法」ともいえる状況の中で、当日早朝に思いついたイメージを手書きで作成。「社会の移り変わり」というタイトルで、最初の「つかみ」のチャートを完成。事なきを得た。それは1988年のことだった。
よくよく見ると、その場しのぎで描いたものの、各種要素の絡みあった興味深い構成である。その後も、同様の図案を描き続けると同時に、「一覧性」の特性を研究しユニークな絵を作成していった。2000年ころより「情報デザイン」や「図解」、「マインドマップ」をはじめ、論理的思考法の概念が発展。今後は、AIの導入により、さらに事象の関係性を重視した図による新たな考え方がでてくるものと期待している。